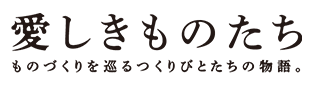本当にやりたいことは何か?それがガラスの世界だった。
代表の克人氏は大学卒業後、建築設計事務所に就職していたが、30代前半で転機が訪れる。それは母の死だった。10代の頃に父親を亡くしていた同氏は、母親まで亡くなったことで死を強烈に意識したという。そこで自問自答を繰り返し、自分がやりたいことをやろうと決意。それがガラスの世界だった。当時、長崎で販売されているガラス製品やお土産などは中国製がメイン。国産でも沖縄のものが多く、長崎産のガラス製品はほとんど無かったという。同氏は東京の学校でガラスを学んでいたが卒業後は帰郷し、長崎で工房を立ち上げることを決意する。「長崎でガラスの火を灯す。そんな使命感を感じたんです」。独立後克人氏は18世紀頃に作られていた冷酒用急須「長崎チロリ」を初めて長崎で復元し、大いに話題となった。その後他の工房でもチロリが作られたが、製作の難しさから、現在製作しているのは瑠璃庵のみとなっている。

長崎ガラスの火を消さないように守る。父と息子の共通の思い。
息子の礼人氏が同じ世界に進む際、父親であり職人の師匠でもある克人氏からは、何の言葉も無かったという。克人氏自身、父親から何も言われないで育ったので「私も息子には何も言いたくない」という理由からだ。純粋にガラスの魅力に取り付かれた礼人氏は、息子という立場を捨て一人の職人として修業を積む。その間も克人氏からは何の教えもなかったそうだが「先輩たちは父から教えてもらっていました。先輩達の技を見ることアドバイスを聞くことが、間接的ですが父からの教えだと思っていました。」と礼人氏は静かに語ってくれた。そんな礼人氏も、この道20年以上になる。個人的な目標について伺うと「長崎ガラスの火を消さないように、この火を今後も守って行きたい」と答えてくれた。克人氏が工房を立ち上げたあの時の意思は、言葉を交わさなくとも受継がれているようだ。

長崎ガラスの代表として、瑠璃庵を世界に広めて行きたい。
瑠璃庵が同地で工房を立ち上げてから、30年以上変わらず続けていることがある。それは、吹きガラス、万華鏡、ステンドグラスなど、手づくりガラスの体験学習を開催していること。「少しでもガラスの魅力を伝えたいという思いから始まったのですが、最近は小学生の時に体験をした方が、大人になって奥さんと一緒に来てくれたり、さらには教師になって生徒を連れて来てくれたりしています」と、当初の願いは見事なまでに結実。スタッフ全員、心から喜んでいるそうだ。
礼人氏に瑠璃庵を牽引していく2代目として将来の展望を伺うと、「瑠璃庵の製品を全世界へと伝播させていきます。この場で詳細は言えませんが、そのための企画・計画はきちんとできています」と熱い言葉が次々に飛び出した。礼人氏は決して多弁ではない。むしろシャイな印象だが、この時の言葉には自信が満ちあふれていた。今後、瑠璃庵が世界で認知されるのもそう遠くないだろう。